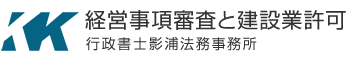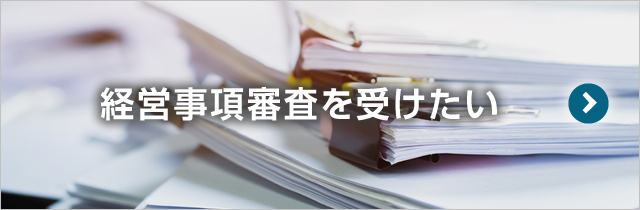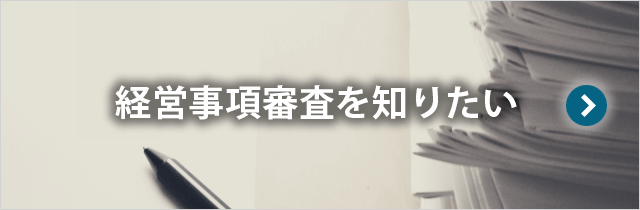建設業許可は、2025年現在、29業種あります。その中の7業種は「指定建設業」に指定されており、他の22業種とは少し違う取り扱いがされることになります。今回は、指定建設業について解説します。
指定建設業7業種
| 業種名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 土木一式工事 | 道路、橋梁、ダムなど、総合的な土木工事 |
| 2 | 建築一式工事 | 建物の新築・改築・増築など、建築全般を含む工事 |
| 3 | 管工事 | 給排水、空調、ガスなどの配管設備工事 |
| 4 | 電気工事 | 電力設備、照明、通信などの電気設備工事 |
| 5 | 造園工事 | 公園や庭園の設計・施工、緑化工事 |
| 6 | 鋼構造物工事 | 鉄骨建築や橋梁など、鋼材を使った構造物の工事 |
| 7 | 舗装工事 | 道路や駐車場などのアスファルト・コンクリート舗装工事 |
これらの7業種は、特に専門性が高く、社会的影響の大きい工事ということで、許可取得の際に他の22の業種とは異なる取り扱いを受けることになり、他の22業種よりも厳格な基準が設けられていることがあります。
指定建設業7業種の監理技術者になるには実務経験だけでは足りない
指定建設業7業種では、監理技術者となるためには一級の国家資格や技術士の資格者、国土交通大臣が認定した者であることが必要です。言いかえると、指定建設業7業種の監理技術者になるには実務経験だけではなることができない、ということです。
現場に向き合っていれば成長していくフェーズ
こつこつと実務経験を積み重ねてきて、建設業許可を取り、会社を少しづつ大きくしてきた建設業者さまが会社を大きくしたい、大きな工事を請け負いたい、と考えられたときに直面することが多い壁の1つと言えるかもしれません。
それまでは積み上げてきた実務経験を証明することで扉が開いてきましたし、建設業許可を取得した後は許可申請関係の書類をきちんと保管していれば何とかなっていたと思います。
建設業許可業者となった後は毎年の決算届(決算変更届)の提出もすることになりますし、5年に1回の更新がありますので、書類をきちんと保管されている業者さまがほとんどです。現場に全力を注いでいればそれだけで事業を大きくしていけるフェーズです。
意識を変えなければいけないフェーズが来る
ただし、特定建設業への切換や監理技術者の配置が要求される工事の請負、というフェーズになると「意識的に」「事前に」「計画的に」準備をしておかなければならなくなります。
技術者の確保、とりわけ監理技術者の採用は、とても難しくなってきています(そもそも数が限られている)。
スーパーゼネコンでも監理技術者の確保は簡単にはいかない
世田谷区の庁舎建て替え工事に関連して、大成建設が監理技術者の交代に際し、同水準の監理技術者を確保できず、違約金を請求された、というニュースがありました。後任の監理技術者はいたものの、前任者と同水準の実績を持っている監理技術者を確保できなかった、というものです。
本庁舎等整備工事における監理技術者の変更に伴う違約金の発生について[PDF]
本庁舎等整備工事における監理技術者の変更に伴う違約金の発生について
本工事現場に配置された大成建設の監理技術者に交代の必要が生じ、この交代において、後任の監理技術者の施工実績が、当初監理技術者が保持していた実績に及ばないことから、 「世田谷区本庁舎等整備工事における技術提案等の取扱いについて(令和3年5月20日)」(以下、「技術提案等の取扱い」という。)に基づき、違約金が発生する見込みとなった世田谷区庁舎整備担当部
建設業界における技術者確保がいかに難しくなっているかを現しているといえます。
現場に配置できる技術者がいない!?
許可申請の際の営業所技術者等は、実務経験のみでなることができるケースも少なくありません。会社が成長し、大きな規模の工事を受注できるようになってきたタイミングで、現場に監理技術者を配置しなければならない規模の工事である場合、指定建設業の7業種だと、監理技術者となれる技術者が社内に居ない、ということが起きてしまうかもしれません。そうなると、この工事を受注し施工してしまうと配置技術者違反となりますから建設業法違反となります。
特定建設業を取得するタイミングで手をうっておく
通常は、監理技術者を配置する必要がある工事を請け負うようになる前に特定建設業許可の取得を検討することになります。特定建設業許可の取得を検討する際に、その業種が指定建設業の7業種に該当している場合は、一級技術者を2人以上確保しておく必要性が非常に高いといえます。技術士の資格者や国土交通大臣が認定した者でもOKですが、人数的にはかなり限られているのが現状なので、一級技術者、という観点で探すのが合理的です。
別の記事でも解説したことがありますが、どの許可業種を取ればいいかで迷ったとき、(迷っても構わない余地がある場合)、この指定建設業7つの中から選んでおく、ということもご検討いただくと良いかと思います。
あわせて読みたい

建設業許可新規申請のときにどの業種を取るべきか
他の22業種と比較して、少し許可取得のハードルが高いので、取得が可能なタイミングで取っておかないと後々の業種追加では取得しにくい状況になることがあります。
指定建設業7業種の注意点をご存知ですか?
当事務所では、建設業許可に関するコンサルティング、許可申請、相談などを承っております。許可申請、経営事項審査、入札参加資格審査申請などはもちろんのこと、特定建設業への切換、業種追加、技術者確保のご相談も承っております。