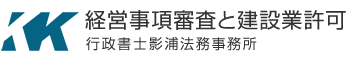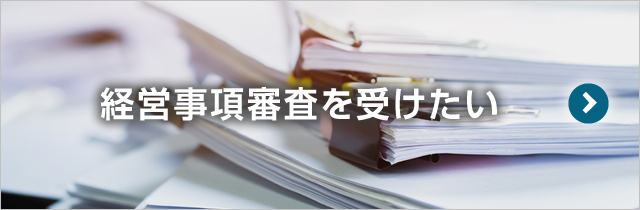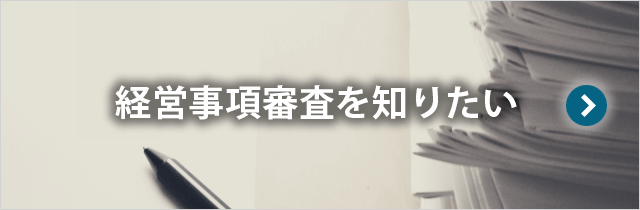入札では入札参加資格審査申請の際に希望業種を選択して申請します。建設業許可を取得する際の業種の考え方と経審や入札の際の業種の考え方では少し違う点があることについて解説していきます。
建設業許可の時はそれほど考える必要がないことも多い
まず、建設業許可取得の際の業種は、資格者を技術者とする場合はそれほど気にしなくてよいケースが多いといえます。取得済みの資格に紐づく業種を取ることになるからです。実務経験10年で取得する場合は、実務経験として列挙していく工事の内容(請負契約のタイトルだけでは決められません)を精査していくことになり、許可事務ガイドラインや、各許可行政庁(都道府県や地方整備局)の手引きを熟読しながら進めていきます。
許可後の決算変更届の業種判断は慎重に行うことが望ましいでしょう。
経営事項審査の時の業種はかなり慎重に考える
経営事項審査の業種判断も工事経歴書に掲載する工事の契約書などを添付しますから契約書の表題だけで判断してしまうと危険です。契約書の表題は民間事業者同士の契約だと特に制約などはないので慎重に検討されることなく決定されてしまうケースがあり得ます。そうなると、工事の実態と契約書の表題が乖離していることも起きてしまいます。
入札の時の業種はブレがあることを想定しておく
入札の場合は建設業許可や経営事項審査とは少し違った点に注意することになります。入札の仕様を決めるのは発注者(市町村や都道府県)ですが、どの業種を指定するかを決める際に建設業法を精緻に検討して業種を決定しているかどうかが確約されていない点を理解しておく必要があります。
もちろん、担当者が適当に決めているわけではないのでしょうが、入札の際の業種を決めている人間(市の担当部署)と許可を審査している人間(県や整備局の担当部署)が異なっている以上、業種の判断にブレが生じるのは避けられません。さらにこの双方が密に連携して検討しているようなこともおそらくないので、このブレは以外と小さくありません。
入札に参加するために必要な業種と実際に施工するのに必要な業種が違う!?
これで何が起きるかといえば、「土木一式を指定されている案件で実は必要なのはとび・土工」のようなことが起きます。落札するにはそもそも参加できる必要がありますから土木一式がないと入札に参加できないので土木一式の許可が必要なのですが、落札後実際に施工するのにはとび・土工が無いと無許可業種を施工してしまうことになります(金額などは一旦置いておきます)。
大事なのは建設業法を基準に判断すること
あくまでも実際に工事を施工するのに必要なのは書類上の名目ではなく実際の工事の内容です。言い換えると、書類上は自社が許可をもっていない許可業種の記載があったとしても実際の工事の内容が許可を持っている業種の工事であれば、建設業法上は全く問題ありませんから安心して工事を請け負っていただいて構いません(ただし、業種の最終的な判断はとても難しいです)。
現場で求められる能力と書類上や業法上求められる能力とではあまりに違いすぎます。書類や建設業法でお悩みのことがありましたら私たち行政書士にご相談ください。