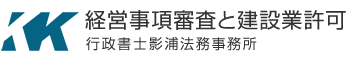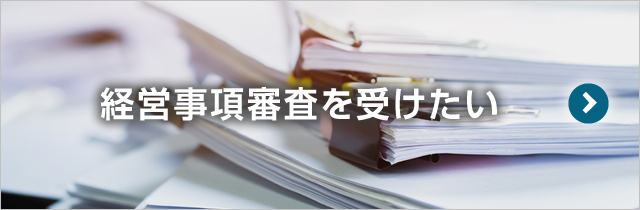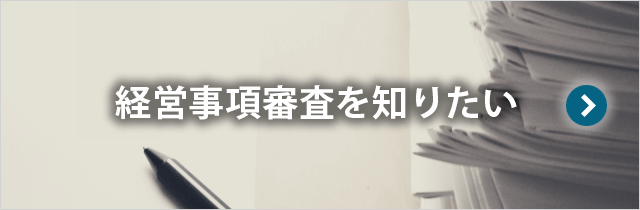建設業許可は取得するのにかなりの労力を要します。そして、せっかく取った許可を維持するのも簡単ではありません。建設業許可を維持するために重要なポイントはいくつかあります。重要なポイントを押さえておけば何かあってもリカバーできる可能性が高くなります。今回は建設業許可を維持するために必要なこと、という視点で解説します。
許可申請の際の「要件」をおさらい
建設業許可申請をした際に許可を取るために必要なポイント(「要件」という言い方をします)がいくつかありました。憶えていますか?
軽くおさらいします。
建設業許可を取得するためには4つの要件を満たしていること、そして“欠格”要件に該当していないこと、です。欠格要件、というのはこれに該当してしまっていると絶対に許可が取れないという項目です。
以前、こちらの記事で解説しました。
あわせて読みたい
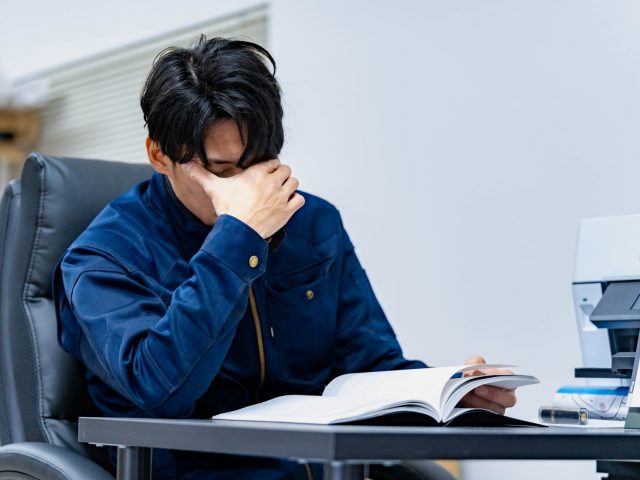
建設業許可を取得できないケースとは
建設業許可に必要な4つの要件
建設業許可に必要な4つの要件は以下のとおりです。
- 建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者がいる(常勤役員等)
- 建設工事について専門的な知識を持った者がいる(営業所技術者等)
- 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれがない
- 工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有している
許可の取得も許可の維持も要件は同じです
建設業許可を維持するために必要なこと、も実はこの4つです。何も変わりません。むしろ、更新の際には4の財産的基礎については緩和されます(一般許可の場合)。ただし、特定許可の場合は、財産要件が欠損の割合(20%未満)・流動比率の割合(75%以上)・自己資本額(4,000万円以上)という要件になっているので、緩和とは言えません。
許可の維持の観点でも一番大変なのは新規許可申請のときと同じく、1.常勤役員と、2.営業所技術者等の確保です。同じ人が在籍しつづけてくれると問題ないのですが、諸事情により退職されてしまうケースは少なくありません。許可を維持する、という観点からは後任候補者の目星をつけておくことも必要になってきます。
忘れがちな変更の届出をきちんと行っておくことが大事
建設業許可を維持するために必要なこと、とは具体的にはこれら4つの要件を維持しつつ、変更事項があった際にきちんと所定の期限内に届出をしておく(届出ができる状態にしておく)ことが中心になります。
全業者が毎年必ず提出しなければならない、決算変更届
この変更の届出、には役員変更や住所変更などもありますが、事業年度(決算)終了後4カ月以内に提出する決算変更届(決算届)も必ず行ってください。
決算変更届をまとめて出すのはやめましょう
毎年出すのが面倒なので更新のタイミングで5年間まとめて提出する、という手法が存在していましたが、大阪府では明確に問題視するようになっています。
複数年度分の決算変更届をまとめて提出することが続くと「処分する可能性がある」と明記した文書を配布しています。決算変更届は毎年度きちんと提出するようにしてください。
この決算変更届(決算届)は、提出していない年度があると更新ができません。
更新期限の直前になって、決算変更届を提出していないことがわかり、該当年度の決算書は紛失してしまった、という事態は最悪です。自社で対応しきれないようなら私たち行政書士を活用していただければと思います。
建設業許可を維持することでお困りですか?
当事務所では、建設業許可を取得できたけど維持するのが難しい、という建設業者さまからのご依頼、ご相談を承っております。