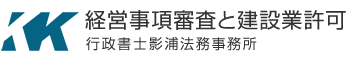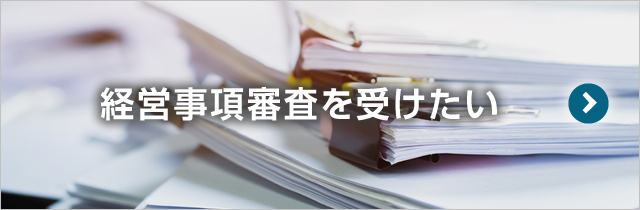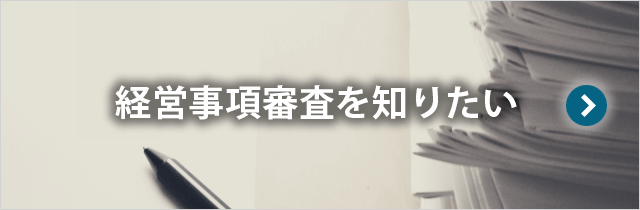会社の規模や請負金額の上昇傾向だけで特定建設業を選べばよいわけではない、という点を前回解説しました。
あわせて読みたい
建設業許可の「一般」と「特定」とは?
それでは、一般建設業と特定建設業のどちらの要件もクリアできそうだという時に、どちらを選べばよいのでしょうか?
会社を大きくしたいなら特定、というような簡単な話では済まないケースがあります。特定建設業を選んだ方が良いケースについて解説します。
財務状況が堅調であること
特定建設業許可は、財産要件の面で一般建設業許可よりも維持するのが大変です。特定建設業許可の財産要件は下記のとおりです。
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本額4,000万円以上
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上
資本金2,000万円は維持するのに苦労はしませんが、欠損の額などは要注意です。
得意先の倒産や、社会情勢のような外的な要因で欠損が膨張することがあります。資材が調達できず工事が進められないなどの事情も考えられます。近年では建築資材全般が高騰していると聞きます。木材や半導体が国内に入ってこないなどのニュース報道をご記憶されておられる方もいらっしゃるのではないかと思います。
許可を取得している全期間において財産要件を維持していることまでは必要ありませんが、更新の直近年にこういった不測の事態が起きてしまうと、特定建設業を維持できない可能性が出てきてしまいます。
1級技術者を安定して確保できていること
特定建設業の許可を取るだけなら技術者は1人いれば可能です。
ただし特定建設業は、工事の規模が大きくなっていますから、現場に配置する技術者は監理技術者を置くことを求められるケースが多くなります。規制緩和の流れはあるものの、営業所技術者等との兼務はまだまだ難しい点が多いため、営業所技術者等とは別に現場に配置する技術者を確保しておく必要性が非常に高くなります。
現場に配置できる技術者が居ないと、特定建設業許可を「維持しているだけ」になってしまい、特定建設業許可が必要とされる工事を受注できない状態になってしまいます。
下請に発注する金額が大きい業態であること
特定建設業許可は「下請に合計5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円)の発注をする」工事を施工する際に必要になる許可です。つまり、全ての工程を自社で100%手掛ける場合や、下請けに発注するのはごく一部、というような業態ですと、そもそも特定建設業許可は必要ないことになります。
請負金額が5億円や10億円であろうが、全て自社で施行するなら一般建設業許可で請け負うことができます。将来的に元請として工事を請けていきたい、という意向をお持ちの建設業者さまの場合は一般建設業から特定建設業へのシフト(般特)を検討してみてもよいかと思います。ただし、これまで解説したように「財務状況を健全に保つ」「1級技術者を安定して確保する」などの対策はしておくことになります。
一般建設業許可か特定建設業許可かどちらを選べばよいかでお悩みですか?
当事務所では特定建設業許可の取得を検討しておられる建設業者さまからのご依頼、ご相談を承っております。一般でいいのか特定を取るべきかのようなお悩みをお持ちでしたらぜひ一度ご相談くださいませ。