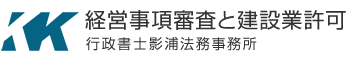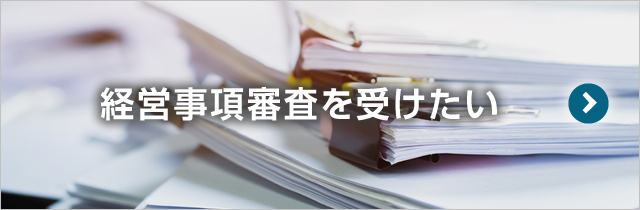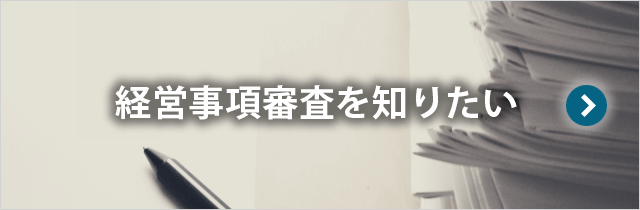特定建設業者への転換に伴う注意点と対策
一般建設業から特定建設業へと転換することで、請け負う工事の幅が広がり、大型案件への参入も可能となります。しかし、その一方で法的・経営的に新たな責任や義務が生じ、知らずに進めると落とし穴にはまる可能性があります。
特定建設業者となった際に特に注意すべきポイントや落とし穴について解説します。
責任の増大
特定建設業者は、下請に出す金額が一定以上となる工事を受注することができます(下の図)。
| 建築一式「以外」 | 5,000万円 |
|---|---|
| 建築一式 | 8,000万円 |
(2025年10月1日時点)
これにより、発注者からの信頼度も高まりますが、同時に工事全体の品質や安全管理について、より重い責任を負うことになります。一般建設業時代よりも、工事全体の進行管理や下請業者への指導・監督が求められることになります。
財務基準・経営基盤の強化
特定建設業者には、許可要件として資本金2,000万円以上、自己資本額4,000万円以上など、厳しい財務基準が求められます。許可取得時にはこれらの基準をクリアしていても、経営悪化や資金繰りの悪化により、基準を下回るリスクがあります。
更新時に資本金2,000万円と自己資本額4,000万円を下回っていると、更新ができません。
欠損の額、流動比率にも注意が必要
資本金の額、自己資本額だけでなく、「欠損の額が資本金の20%を超えていない」「流動比率が75%以上」であることもクリアしておく必要があります。
一般建設業では新規申請時の財産要件は問われなくなりますのでこのような仕組みはありません。特定建設業だけの仕組みです。財務諸表の定期的な確認や資本強化策の検討を怠ると更新できない可能性が出てきてしまうため、常に経営状況を把握し、早めの対策が必要になります。
下請業者管理の厳格化
特定建設業者として元請工事を多く手掛ける場合、下請業者の選定や契約、指導・監督に関する責任が一層重くなり、下請業者の選定基準や契約内容の見直し、現場での安全衛生管理、法令遵守体制の構築など、管理体制の整備が不可欠です。
特に、建設業法や下請法、労働安全衛生法など関係法令を順守しないと、処分対象になってしまうことも考えられます。

熱意のある建設業者様こそ要注意
建設業界では、親方が独立してコツコツと工事を積み重ねて売上を上げ、特定建設業者に転換された会社は珍しくありません。許可が不要な規模(軽微な工事)から実績を積み重ね、→一般建設業→特定建設業、と階段を1つずつ上っていくような建設業者さまがたくさんあります。
お客様と向き合い、現場に情熱を傾けて取り組んできた会社ほど、「よい良いものを造る」ことに傾倒するあまり、建設業法や下請法、労働安全衛生法などへの理解が後回しになってしまうことがあります。
特定建設業者になると、より厳しい目で見られることになり、罰則も増えることになりますので、一度立ち止まって関係法令のコンプライアンスチェックをするくらいの心構えでいいかもしれません。
保険や保証体制などの見直しが求められる
大型工事を請け負う場合、施工ミスや事故による損害賠償リスクも高まります。従来以上に工事賠償責任保険や労災保険への加入内容を見直し、不測の事態にも対応できる体制を整えることが重要です。元請としての立場から、下請業者にも適切な保険加入を義務付ける必要があります。
人材・組織体制の強化、技術者の確保
特定建設業者として大型案件を受注する場合、現場管理者や技術者の数・質ともに高いレベルが求められます。一級資格者や監理技術者が典型例ですが、こういった資格を有している技術者を複数名確保しておかないと、特定許可が必要な規模の工事を請け負えなくなります(1名は営業所技術者等として、営業所に常勤することになるため)。
書類作成や管理業務が複雑化する
特定建設業者では、建設業法や労働基準法、下請法など、さまざまな法令に基づく書類作成や報告義務が増加します。契約書、施工計画書、作業報告書、安全衛生管理計画など、提出先や内容も多岐にわたります。
コンプライアンス体制の徹底
社会的責任がより強く求められます。談合や下請けいじめ、不当な労働環境など、社会問題への対応も重要です。社内規程や倫理規範の整備、定期的な社員教育を実施し、コンプライアンス意識の向上を図る必要があります。
資金繰りやキャッシュフローの管理
大型案件では、工事期間が長期化することや、下請業者への支払いが先行することで、資金繰りが厳しくなるケースも少なくありません。特定建設業者への移行を機に、キャッシュフロー管理の仕組みを見直し、金融機関との関係強化やファイナンス戦略の再構築も検討してください。
更新年度1年前の自己資本額に要注意
特定建設業許可を取得した後、更新を迎える年度の直前期の財務状況には細心の注意を払ってください。
例えば、下記のようなパターンになります。
| 許可取得 | 2020年9月 |
|---|---|
| 更新 | 2025年9月 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| チェックポイント | 2024年4月~2025年3月期の自己資本額 |
資本金を減資することはあまりないですが、コロナ禍とかリーマンショック、大規模災害などで単年の決算の数字が悪化することはあり得ます。更新の際に提出する財務諸表上、自己資本額が4,000万円を下回ってしまうと、「特定建設業許可の財務上の要件を欠くので更新ができない」ことになります。
一方で、一般建設業許可の場合だと、新規許可申請の際に求められる財務上の要件「500万円以上の資金調達能力」という要件は「建設業を営んでいるため、要件はクリアしていると推定」する取り扱いがあり、500万円の資金調達能力の証明は免除されます。
特定建設業許可の維持でお困りではありませんか?
一般建設業から特定建設業へと転換することは、ビジネスチャンスの拡大を意味しますが、それと同時に多くの法的・経営的責任を負うことになります。自社の現状や将来計画を十分に見極め、体制強化・リスク管理を徹底することで、落とし穴を回避し、持続的な成長につなげていきましょう。