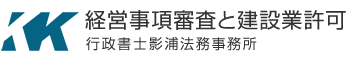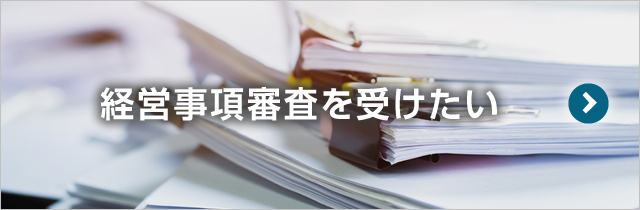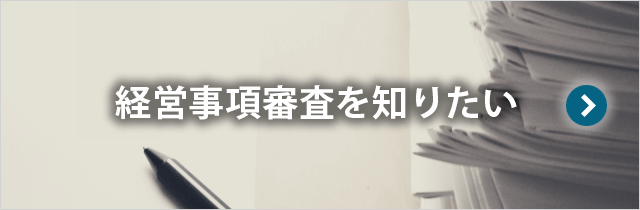入札は参加条件をクリアすれば誰でも参加でき、地方自治体から直接公共工事を受注できる仕組みですが、落札できる件数に制限がある場合があることをご存知でしょうか。
入札(公共工事)は公平性や公共性が重視される
入札は誰でも参加できるという意味では公平なシステムですが、何も制約をつけないと資金力に勝った大手が全部持って行ってしまいかねません。入札の原資は税金ですから、公共性公益性の視点が欠かせません。原資である税金も地方税がメインになるでしょうから、地域性の視点も重要だと推測できます。
市外の業者が落札するとどうなるか
例えば、A市の入札を遠方の都道府県にあるB市の建設業者が全て落札してしまったら何が起きるのでしょうか。A市が徴収した税金を使ってB市の業者を儲けさせていることになります。B市の業者はB市に納税しますので、A市の税金がB市に流出しているようにとらえることができてしまいます。もちろん、そのことだけで悪いことにはならないのですが、程度問題ではあるでしょう。
各自治体は入札に色々な工夫をしています
こういったことにならないように各自治体は入札に様々な工夫をしています。例えば、地元(市内)業者優先のルールです。入札の評価ポイントは入札価格と経営事項審査P点が大きな意味をもっていると考えられますが、もう一つ大きなポイントが事業所が市内にあるかという点です。事業所が市内にある業者であれば先ほどの例に挙げたようにA市の税金が市外へ流出せず、A市が税金を投じて行った事業でA市の業者が利益を上げ、A市に納税するサイクルが生まれます。
入札には落札できる数に制限があることがあります
もう一つは入札で1年間に落札できる件数を制限しているケースです。公表している自治体とそうでない自治体があるかと思います。ルール上、制限していなかったとしても同じ業者が他の業者を押しのけて何件も受注するようなことは考えにくいでしょう。
入札にかけずに発注するには合理的な理由があることが多い
自治体が公平性を軽視してまで特定の事業者に発注する例は存在するのですが、それは災害復旧など緊急性が高く一刻も早い対応が求められるとか、技術的に他に対応できる事業者が存在しないとか合理的な理由が必要になります。入札が一度不調になると随意契約で発注している自治体もあると耳にしたことがあります。この場合でも「入札にかけたが不調になった」という合理的な理由があるといえるのかもしれません。
入札の仕組みなどでお困りではありませんか?
入札の仕組みや自治体ごとの特色などは参加するまでは意外と分からないことも多いでしょう。入札のことでお困りでしたらぜひ一度ご相談してみてください。