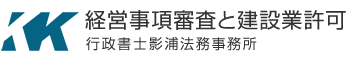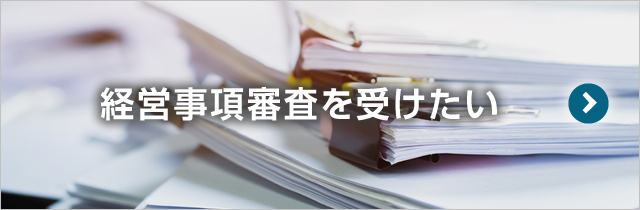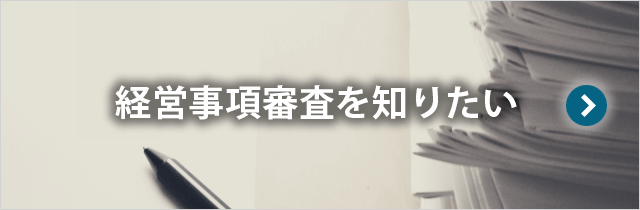入札には民間事業者同士の契約とは異なる点がいくつかあります。そのうちの1つが「地元業者優先ルール」です。入札で優遇される地元業者について解説します。
入札の財源は税金である
これまで何度か解説してきましたが入札の原資(財源)は市民から徴収した税金です。そのため、民間よりも公共性や公益性が重視されることになります。
入札業者を選定するのに「直感で決めた」や「ご縁があった」では理由にはなりません。民間企業では直感で決めたりご縁があったから契約した、でも全く問題ありませんし、それで何事もなく上手くいくことはよくあります。
落札者は1番安い価格で入札した業者で決まるわけではない
入札にかけられ、複数の業者が落札価格を入札したとして、1番安い価格で入札した事業者が必ず落札できるわけではありません。例えば最低3,000万円はかかるような工事入札に1円で入札した事業者に落札させたらどうなるでしょうか。普通に考えてみると施工完了できるとは思えません。
最低落札価格を下回ると落札できない
こういうような事態をあらかじめ回避するために「最低落札価格」を設定していることがあります。X円以下で入札した事業者は落札できる権利がなくなり失格になるというものです。もちろん、X円以下で入札した案件以外では失格になったりはしませんので他の案件には影響しません。
入札金額は一定の幅の中に収まっていないと落札できないことがある
発注予定の案件にはそれぞれ予算の上限もあります。最低落札価格とは逆の「落札上限価格」です。Y円以上で入札した事業者に落札されると予算オーバーのため、落札させない仕組みです。入札に参加した全事業者が落札上限価格以上でしか入札していないと入札が成立せず不調となります。応札した事業者が1つもない場合も不調となります。

入札で地元業者を優先するのには理由がある
地元業者優先ルールも、入札の原資(財源)が税金であることと、公共性や公益性が重視されることから説明することができます。自治体は住民から税金を徴収し、自分たちの自治体・住民のために予算を組み、支出します。使い道が良ければ住民が増えたり地元の業者が潤ったりして税収が増えます。どこの自治体もこのサイクルを重視します。隣の自治体のことは隣の自治体が主体的に考えるべきことです。
都道府県は中小企業の受注機会の増大に取り組んでいる
どこの都道府県でも県下の企業が潤って税収が上がることを期待しています。たいていどの都道府県でもこのことを条例で定めて明記しています。
県として県内の都道府県の企業の受注拡大に取り組まなくてよい理由は思い当たりませんよね。
地元企業優先を明記していてる例
全国各地の自治体がこのような地元企業優先を明記し、公表しています。
東京都千代田区の例
(1) 千代田区内に本店若しくは支店又は営業所を有する者
大阪府箕面市の例
第4条 指名業者の選定は、次に掲げる事項に留意し、総合的に行う。 (8)地域内業者の保護育成のための配慮 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等に基づき、地域内中小企業建設業者の保護育成のための配慮をすること。
市外業者が落札すると市の税金が市外に流れてしまう
入札の落札業者選定もこのサイクルの中に存在します。地元業者(市内業者)に発注することで地元業者の売上が上がり、利益が増えれば税収が増え、次の施策に繋がっていきます。落札するのが市外業者ですと、地元住民から徴収した税金を市外に流出させてしまうような状況になります。
地元(市内)業者には加点がある
入札参加資格審査申請の際に建設工事カテゴリであれば経営事項審査結果通知書を添付します。そのP点を基礎に「地元点+100点」のような感じで地元業者に優遇措置を与え、入札参加事業者を採点していきます。このあたりの点数の比重は自治体によってかなり違いますので一度入札参加資格審査申請の要領などで確認してみてください。
P点、地元加算点、入札価格、事業計画の内容などを総合的に判断して落札業者が決まっていきます。入札価格が重要なことに変わりはありませんが、それだけでは落札は決まりません。
入札に地元業者優先のルールがあることをご存知ですか?
入札に参加してみたいけど、どこの自治体に参加すればいいかわからないなどのお悩みをもったことはありませんか?
当事務所では入札、建設業許可、経営事項審査のご依頼、ご相談を承っております。