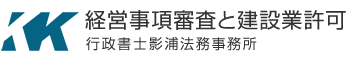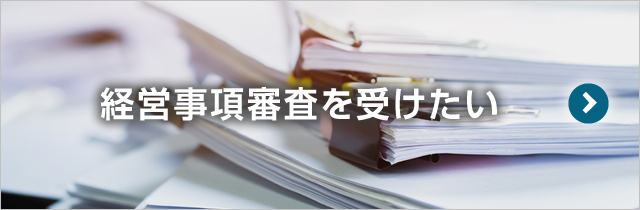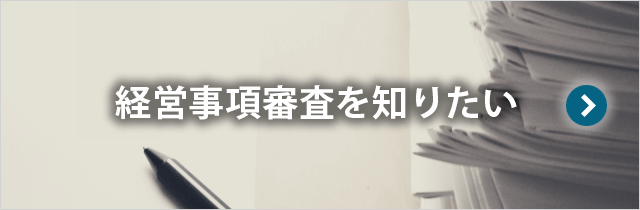入札は都道府県や市区町村、官公庁といった行政から直接仕事を請け負える制度です。入札を活用して事業拡大を目指したい場合、どのような方法が考えられるでしょうか。入札参加をふまえた事業拡大戦略について解説します。
建設業者の皆様にとって入札は身近なものでしょうし、よく耳にするワードではないかと思います。ところが他業種から建設業にスライドしてきたり、建設業許可は必要に迫られて取得したけれど、今もメインの事業は違う業種である場合には意外と入札について知らない、という方も少なくないようです。建設業以外のサービス業の会社様だと入札という仕組を全く知らない、という方もいらっしゃるかもしれません。
入札は建設工事と物品役務に分かれます
入札(入札参加資格)には、一般的に建設業者向けの「建設工事」とその他の事業者向けの「物品役務(委託)」という2つのカテゴリがあります。建設工事のカテゴリは建設業許可、経営事項審査が必須になります。物品役務(委託)のカテゴリは特に参加条件のようなものは設定されていないことも多いでしょう。
入札に参加すると不況に強くなりやすい
入札は行政から直接仕事を請け負える仕組みのため、良くも悪くも民間の景況感の影響を受けにくくなっています。そのため、好景気の際には利益率が確保しにくく魅力が感じにくくなりがちである反面、不景気の際には仕事が途中で無くなったり、発注者が倒産して未払いになったりする心配がほぼ無いため、非常に魅力的に感じます。
入札に参加すると知名度を上げられる
また、入札は地域に密着したものになるため、社会的な信用や知名度が上がりやすくなります。行政は発注した業務の完遂をなによりも重要視する傾向が強いため、「この案件を果たして本当にこの事業者に発注してよいのか?」という点に強くこだわります。建設工事で建設業許可だけではなく、経営事項審査も義務付けている点からもこの点は読み取ることができます。さらに、入札参加資格取得から何年かは実質受注できないようなルールが存在している自治体があると耳にしたこともあります(すぐ倒産しないか、許可や経審の維持コストを継続的に負担できる会社か、などを観察しているのかもしれないですね)。
今回は、建設工事のカテゴリの入札を活用して事業拡大を目指す方法についてもう少し掘り下げていきます。
建設業界はたくさんの人や会社との関わりで成り立っています
建設業界は自社単独で完結することが少ない業界といえるかもしれません。ある程度の規模の工事になるとたいてい下請業者が関与することになります。建設業許可の業種の考え方や配置技術者、特定建設業・一般建設業、大臣許可・知事許可というように複数の建設業者が関与しあって成り立っている業界であることを前提に建設業法が設計されています。つまり、建設業界は他の業界よりも業界内の繋がりが濃いといえるでしょう。
入札に参加する、ということは業界内に名前が売れていくきっかけになりやすい(入札の情報は公開される)ため、「どこどこにこういう業者がいるんだ」と知られるきっかけになります。知ってもらえることが増えると声がかかることも増えていきます。
協力会社と一緒に売上を増やしていく
建設業界は人手不足が常態化しつつあるので、新しい協力先を探している建設業者は少なくありません。入札に落札制限がかかっている地域だと、1社単独では限界がすぐ来ますが、協力会社が多いと、協力会社同士で連携してA社落札工事にB社が下請で入り、B社落札工事にA社が下請で入るというようなこともできるでしょう。