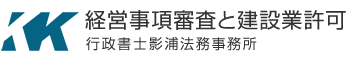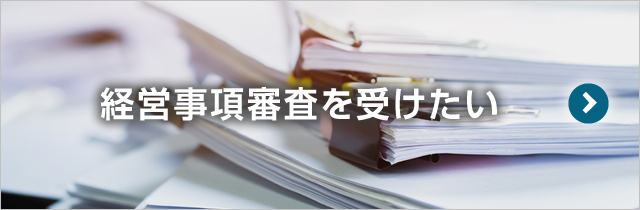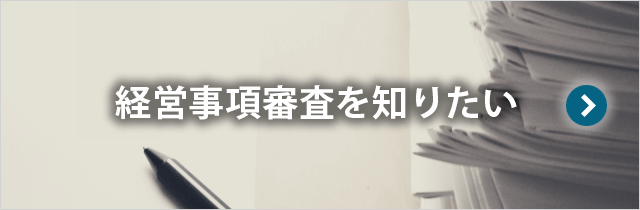対外的な信用が上がったり、請負代金の未回収の恐れがない入札ですが、デメリットなどはあるのでしょうか?入札に参加するデメリットについて解説します。
落札しなくても経審などの費用がかかる
入札に参加するためには、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格の3つが欠かせません。なかでも経営事項審査は毎事業年度終了後に受審することになります。そのため、経営事項審査の費用やその手続きにかかる人手は毎年必要になります。建設業許可は5年に1回の更新、入札参加資格は2~4年に1回の受付(定期受付)、という流れなので、更新や定期受付が無い年度はほとんど費用はかからないことになります(建設業許可の決算変更届に関する費用は別)。
入札参加資格の期限内は経審の有効期限も維持し続けておく必要があります。そのため、実際に1件も落札しなかったとしても経審だけは受け続けなければなりません。
公共工事の利益率は高くないことが多い
公共工事の発注は原資が税金ですから、無駄遣いとなるようなことは避けなければなりません。そのため、民間の工事に比べると利益が出しにくいことがあります。その反面、買いたたきなどもないので少ないながらもきちんと利益が見込めるもの多いといえます。
一定の価格以上でないとそもそも落札できないことがある
入札の仕組みが「一番安い価格で入札した人」を選ぶことなので利益がたっぷり出るような価格で入札しても落札できないことになります。ただし、価格だけで決まらないことも多く(施工業者が赤字になって完成させられないとなるとそれも困るため)、最低落札価格が設定されているケースは珍しくありません。
事務手続きが多い
入札は対行政との契約になるため、民間同士の工事契約と比べると事務的な手続きや書類のやり取りは増える傾向があります。
制約が多い
入札案件は金額や工期などが事前に決まっているため、落札できた場合は決められた内容で完成させることが求められます。工事を進めていくうちに材料費の高騰や想定外の支出が必要になった場合などで契約金額の変更が必要になった場合、価格(や工期)変更契約をまきなおすことになります。
実際にこれだけかかったから、と当初の契約金額を超過する請求書を自社の都合で出しても、契約変更を済ませていなければその金額で支払ってもらえないのではないかと思われます。
別件で急ぎの好条件の工事を請け負えそうだから入札案件の工期を少し待ってもらって、というようなことも難しいでしょう。このように入札に参加すると(落札すると)スケジュールの面では柔軟に対応しにくくなることが予想され、これらのことはデメリットになってしまうかもしれません。
入札に参加するか参加しないかでお悩みですか?
行政書士影浦法務事務所では、入札、経審、建設業許可に関するご相談を承っております。