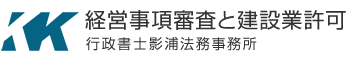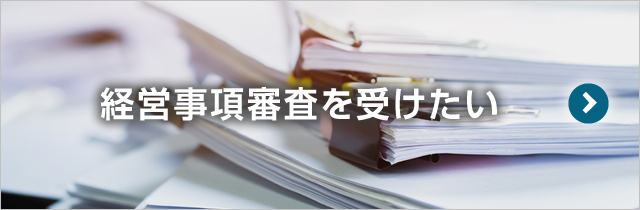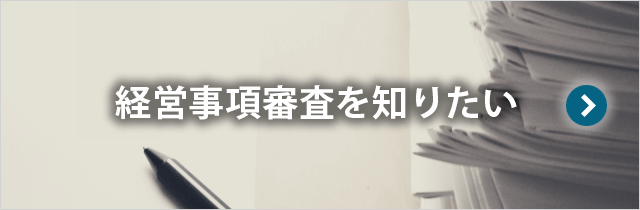建設業許可を取得する際、どの業種を取ればいいのかで悩んでいませんか?
ご自身で検討するまでもなく、得意先の元請さんから例えば「内装工事業の許可を取ってほしい」といわれるケースもよく耳にします。
そのような場合であっても、建設業を専門にしている行政書士なら必ずその業種で本当によいのかを検討します。「内装工事業」の許可が最も適しているかをきちんと分析しないと、本当に必要な業種ではない業種の許可を取得してしまうかもしれません。行政書士に相談するタイミングで一番効果的なのは、このタイミングといえるかもしれません。
あわせて読みたい
建設業許可をこれから取得したい場合は何からはじめたらよいか?つまづきやすいポイントから解説します
許可業種は時間をかけて決める
最初に取得したい業種を絞りこんでいただきたい理由は、建設業許可申請まで時間を確保し最大限活用するのが目的です。確保できた時間で絞りこんだ業種の許可を狙い通りに取得するためです。建設業許可で一番ネックになるのがいわゆるケイカン(経管)とセンギ(専技)呼ばれる人たちです。
現在は、ケイカンは「常勤役員等」と呼ばれたり、そもそも特定の1人でなくても体制として確保できていればよいとされました。建設業の経営を管理する役どころです。センギは、「営業所技術者等」と呼ばれ、建設業の技術を担う人です。
常勤役員等と営業所技術者等は兼務が可能
外部から採用するのでなければ常勤役員等と営業所技術者等は代表者(社長)がどちらかを担うか、兼務することが一般的です。その人さえいれば許可を維持することができるからです。兼務させずに別の人に分けると、どちらかの人が社内にいなくなると許可を維持できなくなってしまいます(後任の人を速やかに確保しなければならなくなる)。社長や代表者が居なくなったときは事業を廃業するケースが多いので、兼務することに合理性があります。
反対に事業の規模が大きくなってくると、今度は誰か1人が欠けても会社を止めるわけにいかなくなります。代表が欠ける(交代する)ことになったしても事業を止めるのが難しいため、常勤役員等と営業所技術者等を分散させることも増えてきます。
取得したい業種が変わると証明する内容が変わる
造園工事業を専門にしてきた方が電気通信工事業をやろうと思っても、土台になっている知識・技術・経験が全く違いますから、到底使えるものではないのはすぐに想像できます。
一方、建築一式工事業や土木一式工事業などの「一式」と呼ばれる工事業は内訳を細かく見てみると、一式工事業以外の27業種の専門工事業の集合体になっています。
建築一式=建築物を建てる、ではありません
例えば、住宅を建てる(建築一式工事)には、基礎工事や足場設置・撤去、外構(とび土工)、大工や型枠・造作(大工)、内装(内装)、配管(管)、配線(電気・電気通信)、屋根(屋根)、シーリング(防水)、とざっくりイメージしてもこれだけの専門業種がすぐに思いつきます。
「一式」工事業はこれら複数の業種にまたがる総合的な工事を企画調整することを「一式」工事と呼んでいるものです。言いかえると、複数の専門業種にまたがって総合的に企画調整する必要がある工事であれば「一式」となる可能性があります。中には、建築物そのものは建てないとしても建築一式工事となるものもあるかもしれません。
家や建築物を建てる=建築一式の許可が必要、とすぐに思ってしまいがちですが、あなたの会社にとって本当に必要な許可が建築一式かとう点はイコールになりません。
建築一式工事業は他の専門業種と違って、建設業許可が必要とされる金額が大きく引き上げられています。建築一式工事業の場合は、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事(税込、材料費含む)までは建設業許可は“必ずしも取得する必要はない”とされています。建築一式工事以外の業種は500万円未満が許可取得のボーダーラインになります。
つまり、このボーダーラインを超えてくる可能性が高い業種の許可が必要になる可能性が高い業種と見ることができます。
受注できそうな内容を予測しておきましょう
建築一式工事を受注していく予定があっても1,500万円未満に収まるとか、木造住宅専門で150㎡未満しかやらないという業者さまが建築一式工事業の許可を取得すると、建築一式工事の1,500万円のボーダーは取り払えますが、内装工事や大工工事などでは500万円未満の工事しか対応できなくなります。
昨今件数が増加傾向のリフォームやリノベーション工事は内容によっては内装工事に分類されるケースも少なくありません。
リフォームを得意としている業者さまであればなおさら業種の選択には慎重に取り組んでいただくことをおすすめします。
どの業種を取るのがよいかでお悩みですか?
当事務所では、建設業許可の取得をけんとうしておられる建設業者さまからのご依頼、ご相談を承っております。
まだ許可申請の予定が確定していなくても問題ありません。むしろ、まだ予定が確定していない状況の方がよいケースも少なくありません。