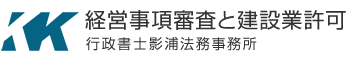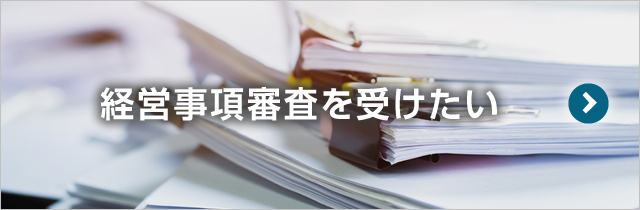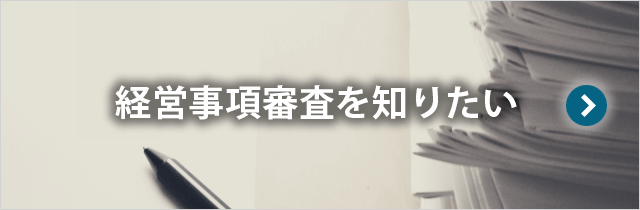建設業許可をいずれは取得したい、建設業許可を1年以内に取得したい、建設業界に参入してビジネスを立ち上げてみたい、というように建設業許可を取得したいと一口に言っても皆様の置かれている状況は様々です。
建設業許可をいずれは取得したい(具体的な期限を決めていない)、建設業許可を○年以内に取得したい(具体的に期限を設定している)、という違いだけでも取り得るアプローチが変わってきます。
まずは取得したい業種を絞りこむのがおすすめ
建設業許可は2025年現在、29種類の業種に分けられています。2種類の「一式工事」と27種類の専門工事に分類されています。まずはご自身がどの業種で建設業をやりたいのかを考えることになります。完全に絞り込みをすることまでは必要ありません。第1候補~第3候補(もちろん、全部取れるなら全部)のような感じでもOKです。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設業の許可とは(国土交通省HPより引用)
どの業種を取得するのが良いか分からないときは行政書士に相談
建設業は業種の境界線があいまいになりがちです。ある工事が29種類のどの業種に明確に当てはまるのかは判断が難しいポイントです。
施主さまからは、たとえば「管工事業の工事をしてください」という依頼をされることはありません。「壁を修繕してください」「住宅を建ててください」「エアコンをこの部屋にとりつけてください」という依頼のされ方がほとんどだと思います。
建設業を専門にしている行政書士なら、日常的に「この工事内容だと業種は何か?」を精査することに慣れています。ご自身がどの業種を取るのが良いかでお悩みになられた場合はぜひ行政書士にご相談ください。
契約書や注文書・注文請書、請求書・領収証などの書類を保管する習慣をつける
建設業許可の申請では、建設業の経験を証明することが求められます。その方法として、請負工事の契約書や注文書・注文請書、請求書・領収証、入金記録などで証明していきます。得意先にも「建設業許可を取りたいと思っているのでご協力をお願いします」と伝えておくのもよいかもしれません。
「面倒だな…」と感じられると思いますが、書類を残していれば許可が取れたのに証明できる資料が残っていないから許可が取れない、という事態になりかねません。
実際は実務の経験はあるのに証明できる資料がなく諦めざるを得ない事例はとても多いです。建設業許可取得後はいずれにせよ請負契約書などの書類はきちんと対応していかなくてはならないので今からその準備をしておくのがおすすめです。
経験を証明する書類は必ずしも契約書でないとダメ、とまではいわれませんが、注文内容の内訳がわかる注文書や発注書のようなもの、それらを確認して請けたことがわかる注文請書のセットで証明していくことになります。
請け負った内容もきちんと後から分かるように掲載しておくと、許可申請時の作業が軽減できます。
犯罪行為をしない、お酒を飲んでケンカしない、飲酒運転をしない
当たり前のようですが、これらが建設業許可などの許認可と直接結びついていることをご存知ではない方が意外と多いです。現場の仕事さえ完璧にやっていれば問題ないのでは?という発想なのかもしれません。
犯罪行為をしない、は言うまでもありませんが、意外と見落とされがちなのがケンカや交通事故です。そしてそれらを一番引き起こしやすいきっかけがお酒です(違法薬物は問題外)。
飲酒運転やスピード違反などでも許可が取れない理由になることがあります。
従業員の最終学歴を確認しておく
建設業許可を取得する際に、技術的な裏付けを持っている人材が必要となります。「営業所技術者等」と呼ばれますが、2024年までは専任技術者という名称で、「専技(センギ)」と呼ばれていたので、今でも「センギ」という呼び方の方が通りがいいかもしれません。
この「営業所技術者等」になりうることを証明する際、実務経験の積み重ねで証明するケースがかなりあります。その方の最終学歴によってはこの実務経験の年数が大幅に短縮される可能性があります。
社会保険に加入しておく
法人さまの場合、社会保険加入は義務です。建設業許可の取得とは切り離されて審査されていた時期もありましたが、今は加入していないと許可が取れないとお考え下さい。
各種人的要件の証明資料として、最も簡単なのが社会保険の加入時です。
個人事業主さまであれば従業員5名未満の場合は適用事業所に該当しないため社会保険の加入義務はありませんが、従業員の中から、いわゆる経管と営業所技術者等を指名したい場合は常勤性を証明する必要が出てきます。
これらを証明する資料としては社会保険に加入することが最も簡単です。
建設業許可を取得したいと考えているが、何からはじめればよいかでお困りですか?
当事務所では、建設業許可を取得したいとお考えの方のご依頼、ご相談を承っております。
今すぐじゃないんだけど…という場合でもOKです。むしろ今すぐじゃない場合の方が効果的にサポートできることが多いです。