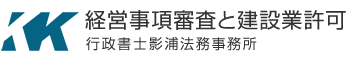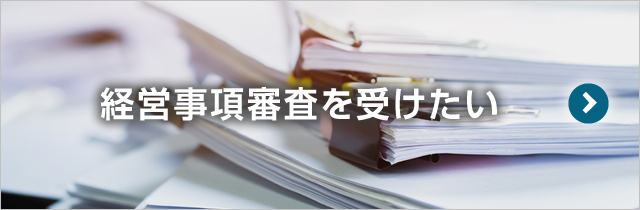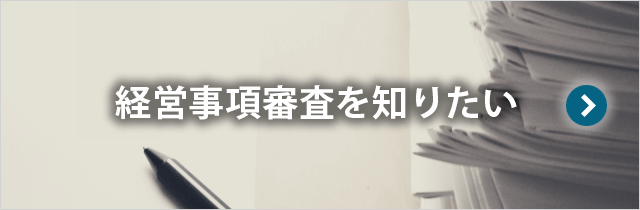将来的に建設業許可を取得して建設業を始めたい、とお考えの方の中にはすでに明確なビジョンをお持ちの方もいらっしゃるのではないかと思います。
建設業許可は、個人事業主でも取得が可能ですが、建設業許可を法人で取得したい、と考えた場合に、何から始めたらよいかについて解説します。個人事業で許可を取得するのと大きくは違いませんが、「法人を設立する」というひと手間が加わることで注意する点が出てきます。
法人の種類はなんでもよい
ほとんどの方は株式会社を設立することを想定されておられるかと思います。株式会社で全く問題ありません。ただ、会社には株式会社以外にもいくつかの形態があります。
株式会社以外にも、合同会社・合名会社・合資会社という種類がありますが、そのどれでも建設業許可の取得は可能です。今回は最も一般的な株式会社を設立して建設業許可を取得したい場合を想定して解説します。
役員(候補)を探す
株式会社では1人以上の役員(取締役)が必須です。あなた自身が1人で取締役に就任されてもよいですが、1つ注意点があります。
役員が欠格要件に該当しないか確認しておく
役員は何人でも構いませんが、役員の中に1人でも「欠格要件」に該当する人がいると、許可は取得できません。欠格要件の分かりやすいものは、下記のようなものです。
- 破産した人
- 建設業法違反をした人
- 禁固以上の刑を受けた人
- 成年後見人がついている人
- 未成年者
- 反社会的勢力と関わりがある人
くわしくは、別の記事で解説しようと思います。
株式会社の役員には、未成年でもなることが可能ですが、建設業許可を取得したい場合は、役員に未成年者を入れないようにすることになります。建設業をはじめとして、行政の「許可」がないとその事業を(一定以上の規模で)営めないものは、だいたい同じような基準で欠格要件に該当しないかをチェックされます。
破産や建設業法違反、禁固以上の刑を受けた、などは決められた年月を経過していれば欠格要件に該当しないことになります。
とくにケンカや交通違反、飲酒運転などは要注意
これらの欠格要件で見落としがちなのが、ケンカして暴力事件になった、とかスピード出しすぎて赤切符切られた、とか飲酒運転などのケースです。
プライベートの範疇で起きたことのように思ってしまって、仕事(建設業)とは関係ないじゃないか、と思われたかもしれませんが、欠格要件として明記されていますので、許可がとれなくなってしまいます。これらが全役員についてチェックされます。
資格を持っている方を探す、自分で資格を取る
建設業許可では、建設業を営めるための技術的な裏付けがあることを技術を有している人材がいるかという視点で判断します。営業所技術者等といいます。少し前までは専任技術者、「専技(センギ)」と呼んでいました。
ご自身が何か資格をお持ちであれば探す必要はありませんが、取りたいと考えている業種の許可が取れる資格かどうかを確認しておきましょう。二級建築士の資格をお持ちであれば建築一式工事業の許可は取得できますが、電気工事業とか土木一式工事業などの保有資格と関連が薄い業種は取ることができません。
取得したい許可業種の資格をご自身で今おもちではないとするとどなたかを雇用するか、ご自身で対応している資格を取得するか、実務経験を証明するかの選択になります。
500万円以上の資金を調達する
株式会社を設立して、建設業許可を取得したい場合、会社を設立してすぐに許可申請をするケースが多いのですが、資本金は500万円以上にするのがおすすめです。資本金500万円未満では許可が取れないわけではないですが、500万円以上の資本金で設立してしまうのが最もスムーズです。
資本金で500万円を用意できなかった場合は、預金の残高証明書で500万円以上の資金調達能力があることを証明します。残高証明で証明する場合、資金「調達」能力なので全て自己資金である必要はありません。借入などでも差し支えありません。
会社の目的に「建設業」といれておく
会社を設立する際には「定款」というものをつくることになります。定款の目的欄には、その会社の事業内容を列記します。ここに「建設業」とか建設業を営むと読み取れる項目がないと、変更登記をすることになり、余分に費用がかかってしまいますので初めから建設業と目的に入れておきましょう。
なお、定款の目的欄に記載した事業以外の事業をすることはできないかというと全くそんなことはありません。
建設業や産業廃棄物処理業、宅地建物取引業などの行政の許認可が必要な事業は定款の目的欄に明記されている必要がある、と理解していただければよいかと思います。行政の許認可が必要ない一般的な事業は定款の目的欄に記載されていなくても事業を行うことができます。
工事契約書や注文書・注文請書、請求書・領収証などの書類を保管する習慣をつける
こちらの記事でも触れましたが、建設業許可申請の際、様々なポイントで「建設業の携わっていた経験があるか」を証明することがあります。その際の証明書類は、工事請負契約書や工事注文書・注文請書などの書類で行うことになります。「建設業の経験があります」というあなたのコメントだけでは証明になりません。
早めに行政書士に相談する
将来的には建設業許可を取得するつもりだが、まだ先の話なので「そのタイミングが来たら相談しよう」とお考えではないでしょうか?
建設業許可申請を得意としている行政書士なら、このサイトやこの記事で解説していることを常に念頭に置きながら皆様と接しています。
法人を設立して建設業許可を取得したい、と相談すれば、「資本金は500万円にしてください」「定款の目的欄はこうしましょう」「取得したい業種はどれですか?」「ケイカン(現、常勤役員等)、センギ(現、営業所技術者等)はどなたの予定ですか?」「資格はお持ちですか?」と聞き出してくれます。
早すぎて(行政書士に)相談されても困る、ということはあまりありません。相談のタイミングがまだ少し先の話なら、今できることや今からやっておくと良いことをアドバイスします。
会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えですか?
当事務所では、会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えの方からのご依頼、ご相談を承っております。まだ具体的な時期は決めていない段階でも大丈夫です。