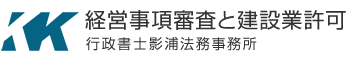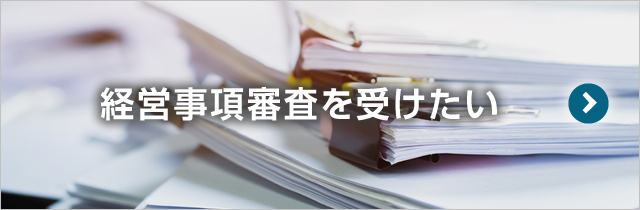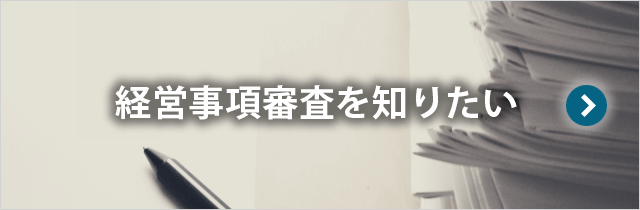新規で建設業許可を取得したい、というご相談をうけたときに、やはり「建築一式工事業」を希望される建設業者さまはたいへん多いです。その際、よく言われるのが「建築一式工事業持っていたらオールマイティーに工事できるでしょう」というものです。
確かに「一式工事」という言葉の響きから、すべてを包括するような印象を受けるのも無理はありません。
しかし、これは大きな誤解です。
「一式」は全部、ではありません
実際には、建築一式工事業の許可があっても、他の専門工事(とび・土工、電気、管工事など)を自由に請け負えるわけではありません。他の専門工事業の許可がないまま工事を請け負うと、無許可営業に該当する可能性があり、最悪の場合は営業停止や許可の取消のような罰則を受けてしまう可能性もあります。
今回は、建築一式工事業の許可の正しい理解と、許可申請を行う上で押さえておくべきポイントや、建築一式工事業はオールマイティーではない点について解説します。
2つの一式工事業とそれ以外の専門工事業
建築一式や土木一式のような「一式」とついている専門工事業は複数の業種にまたがる総合的な工事を企画調整することを「一式」工事と呼んでいます。建築一式なら、とび土工や大工、屋根、内装、塗装、管、などの工事が含まれていることはイメージしやすいと思います。このように複数の専門業種が含まれている工事を請け負えるから「オールマイティー」だと勘違いされていると思われます。
建築一式工事業はさきほども触れたように「複数の業種にまたがる総合的な工事を企画調整する」ことを求められています。さきほど例示した、とび土工(足場や基礎)、大工(木造建築)、屋根(瓦)、内装(インテリア)、塗装(ライニング)、管(配管)などの個別具体的な工事を施工するにはそれぞれの専門工事業が必要になります。
総合的に企画調整し、必要に応じて個別具体的な専門工事は該当する許可業種を持っている下請に発注することになります。
建築一式工事業しか取得していない状況で、新築工事(建築一式)を受注し、新築工事に含まれる例えば大工工事を施工してしまうと無許可の大工工事を施工してしまったことになります。
一式工事と専門工事の違い
建設業許可制度においては、以下のような業種分類がされています。
| 一式工事業 |
建築一式工事業 土木一式工事業 |
|---|---|
| 専門工事業 | とび・土工、内装仕上、電気、管、屋根、防水など27業種 |
ここで注意すべきなのは、一式工事業と専門工事業は別の許可業種であるという点です。
たとえば、建築一式工事業の許可を持っていても、
| 電気工事のみを500万円以上で請け負う場合 | 電気工事業の専門工事業の許可が必要 |
|---|---|
| 内装工事のみを500万円以上で受注する場合 | 内装工事業の専門工事業の許可が必要 |
つまり、一式工事の許可=万能ではないということです。
建築一式工事業」で対応できる範囲
では、建築一式工事業の許可があれば、どこまで対応できるのでしょうか?
複数の専門工事を組み合わせて行う「建築物の建設」を目的とする工事
たとえば、新築住宅の建設で、基礎、屋根、内装、電気などを一括で請け負うようなケースは、まさに建築一式工事業が想定している工事内容といえそうです。
「建築物の建設」を目的とする工事の中に500万円を超える専門工事がある場合
ただし、先ほどの建築一式工事業が想定している工事内容の中に、例えば500万円を超える内容がある場合は、該当する専門工事業の許可を求められる可能性が高くなります。
例えば、次のようなケースだとイメージしやすいかもしれません。
・屋根に高級な瓦をふんだんに使用したため、屋根だけで500万円を超えてしまった
・特注品の建築材料をたくさん使ったので内装に700万円かかってしまった
どちらのケースでも建築一式工事業だけで対応できるか?というと 建築一式工事業のみでは対応できないという回答になります。
よくある誤解とリスク
| 誤解①:建築一式の許可があるから、内装だけの工事も請けられる | NG。内装のみ500万円以上なら内装仕上工事業の許可が必要 |
|---|---|
| 誤解②:実態は一式工事だから、請負契約書の記載を調整すればOK | NG。行政は契約書だけでなく工事の実態を見て判断します |
| 誤解③:元請だから一式で処理できるはず |
NG。工事の実態を見て判断されます 内容によっては、元請・下請に関係なく専門工事の許可が必要 |
これらの誤解をしたままだと、意図せず建設業法違反となるリスクがあり、信頼や取引機会の喪失につながりかねません。
建設業許可は戦略的に取得すべき
建設業者として事業を拡大していくためには、自社の実際の施工内容に合わせて、必要な業種の許可を戦略的に取得することが重要です。
どの業種を取ればよいか、業種についてはどのように考えるとよいかについては、別の記事で解説しています。
あわせて読みたい
建設業許可を取得する前に取りたい業種を絞りこんでおいたほうがよい理由
たとえば、
| 内装工事の案件が多い | 内装仕上工事業 |
|---|---|
| 電気通信工事がメイン | 電気通信工事業 |
| リフォーム案件で複数業種にまたがる | 建築一式工事業+内装工事業+専門工事業 |
このように、「どんな仕事をしているか・どんな案件を受けていきたいか」を明確にし、それに合致した許可を整えておくことが、機会損失を防ぎ、コンプライアンスの面でも安心です。
建設業許可はプロに任せるのが安心です
建設業許可は、要件確認から書類収集、行政対応まで煩雑で時間もかかります。また、業種の選定を誤ると、本来必要な許可が取れておらず、後から軌道修正が必要になることも。
修正で済めばよいですが、実務経験で営業所技術者等を選定していたりすると、2つ目の業種の経験年数が足りず、別の職人さんを雇用しなくてはならないかもしれません。
当事務所では、建設業専門の行政書士として、業種選定の段階から丁寧にヒアリングし、御社に最適な許可構成をご提案しています。
「建築一式工事業の許可だけでいいのか?」
「今後を見据えてどの業種を取っておくべきか?」
といったご相談も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。