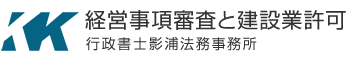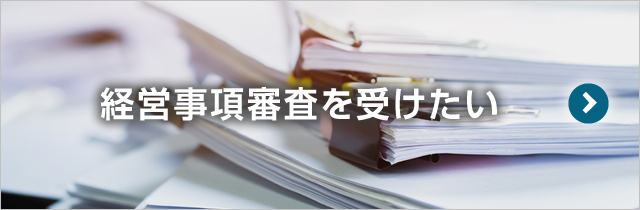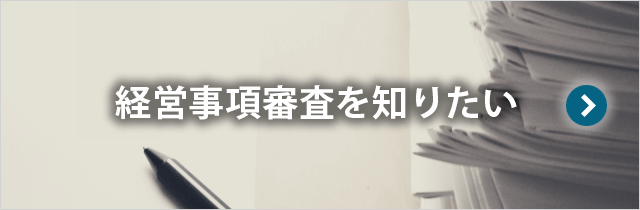建設業の許可が求められる条件はいくつかありますが、一番お馴染みのものは、請負金額ではないでしょうか。客観的な基準ですし、憶えやすい数字でもあり、また、ここしばらく変わっていないという点も挙げられます。請負金額500万円以上(建築一式は1500万円)の建設工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
特定建設業の金額基準は下請代金5,000万円以上
特定建設業が必要になる金額の基準、という線引きもあり、現在は下請代金が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になると、特定建設業を取得する必要があります。
請負代金5,000万円以上でも特定建設業が要らないケースがあります
よくある誤解の1つに「工事請負代金が5,000万円以上になると特定の許可が要る」というものがありますが、全ての工程を自社で施工する場合などは請負金額がいくらになろうが一般建設業許可で差し支えありません。
一方で、工事請負代金が上がってくると、自然と下請代金も同時上がってくることがほとんどでしょうから、そう遠くない将来のために特定建設業許可の取得に備えて準備しておく、ということが合理的な判断となりやすい面があります。このあたりは、自社の工事内容や経営方針によりますので、まずは建設業許可を得意としている行政書士に相談してみるのがおすすめです。
時代と共に引き上げられてきた金額基準
そもそもの建設業許可が必要になる金額、特定建設業許可が必要になる金額(下請代金の額)、どちらも金額による線引きがありますが、それぞれ時代とともに引き上げられてきています。特に、特定建設業の基準は、平成7年から約20年間据え置かれていました。平成7年からの基準は3,000万円以上、建築一式4,500万円でした。これが平成28年にそれぞれ4,000万円と6,000万円に引き上げられ、令和5年に4,500万円と7,000万円に、令和7年には5,000万円と8,000万円となりました。
建設業許可:500万円(消費税率3%)
特定建設業:3,000万円(建築一式4,500万円)
■平成28年
建設業許可:500万円(消費税率8%)
特定建設業:4,000万円(建築一式6,000万円)
■令和5年
建設業許可:500万円(消費税率10%)
特定建設業:5,000万円(建築一式8,000万円)
これには、材料費の高騰や人件費の上昇などの社会的な情勢の影響を受けたものと考えることができます。
「建設業許可」の金額基準は30年以上、上がっていない
では、いわゆる「建設業許可」の基準はどうでしょうか。こちらは平成6年12月に500万円以上、建築一式1,500万円以上という基準が設けられてから令和7年になっても引き上げられることなく、今も維持されています。
建設業許可の金額ボーダーライン
特定建設業:3,000万円(建築一式4,500万円)
特定建設業:4,000万円 ↑ 33%UP (建築一式6,000万円 ↑ 33%UP )
特定建設業:5,000万円 ↑ 25%UP (建築一式8,000万円 ↑ 33%UP )
金額基準が据え置かれることで起きていること
材料費の高騰や人件費の上昇は、特定建設業にしか起きない事象ではありません。軽微な工事しか請け負っていない建設業者さまでも同じ影響をうけているはずです。
つまり、以前よりも「建設業許可を取得しないと請け負えない工事に分類される可能性が上がっている」と言えます。
消費税率は3度上がっている
建設業許可で度々登場する金額の基準には、消費税を含めることになっています。500万円、というのは税込で500万円未満か500万円以上か、で線引きがされることになります。そして、消費税は平成6年以降、消費税率だけを見ても3%→5%(平成9年)→8%(平成26年)→10%(令和元年)と、3度上がっていますが、建設業許可の金額基準はこの間1度も変わっておらず、500万円のままです。
材料費や人件費が上がっていなかったとしても、工事代金が上がりやすくなっているのです。
500万円(建築一式1,500万円)には、材料費も「含む」
もう一つ、気を付けなければいけないポイントに、これらの金額基準には材料費も含む、という点です。建築資材に限らず、社会全体で物価が上昇していますから、材料費も当然上昇傾向になります。
これらの状況を総合すると、以前と同じように工事を請け負っているだけなのに、許可取得(や特定建設業への許可切替)の必要性が高まってしまっているといえます。
請負代金がボーダーラインを超えそうでお悩みですか?
当事務所では、建設業許可が必要か?必要になりそうか?特定建設業が必要か?という点でお悩みの建設業者さまからのご依頼、ご相談を承っております。